先生があなたに伝えたいこと
【北口 和真】脊椎の手術に内視鏡を取り入れ、できるだけ身体への負担がかからない方法で手術を行っています。【佐原 啓太】内視鏡を使った低侵襲手術は身体へのダメージが少ない分、入院期間が短いこともメリットです。

一般財団法人 住友病院
きたぐち かずま
北口 和真 先生
専門:脊椎脊髄
北口先生の一面
1.最近気になることは何ですか?
医師になってからテニスを始め、10年ほど続けていました。けれど、結婚して子どもができてからは時間がとれずプレーできていないので、子育てが落ち着いたら再開したいです。
2.休日には何をして過ごしますか?
小さな子どもが2人いるので、子どもたちの世話や相手をしています。幼児のやることは突拍子もなく、一時も目が離せないので仕事よりも大変な気がしています。

一般財団法人 住友病院
さはら けいた
佐原 啓太 先生
専門:脊椎脊髄
佐原先生の一面
1.最近気になることは何ですか?
スポーツは何でも好きなので、競技が開催される時期に応じて、野球やバスケットボール、サッカーなど、それぞれ注目してスポーツ観戦を楽しんでいます。
2.休日には何をして過ごしますか?
大学時代にアメリカンフットボールをやっていたこともあり、休日はチームドクターとして試合に帯同しています。うちも子どもが小さいので世話もしています。
Q. 脊椎における「低侵襲(ていしんしゅう)手術」とは、どのようなものですか?
A. 北口先生:低侵襲とは身体にかかる負担が小さいことを意味し、技術の進歩によって患者さんに優しい手術が行われるようになってきています。脊椎の疾患には、加齢によって神経の通り道が狭くなる腰部脊柱管狭窄症(ようぶせきちゅうかんきょうさくしょう)や、椎体と椎体の間でクッションの役割を果たす椎間板(ついかんばん)が飛び出て神経を圧迫する腰椎椎間板ヘルニアなどがあります。これらの疾患の神経の圧迫を取る手術として内視鏡を使い、小さな切開をするだけで済む手術が低侵襲手術です。
佐原先生:患者さんに手術の説明をすると、多くの方がまず「何日入院しますか?」と質問されます。現役世代の方が、どれぐらい会社を休まなければならないのか気になるのはごもっともだと思います。低侵襲手術は身体へのダメージが少ない分、入院期間が短縮できるのもメリットです。
![]()
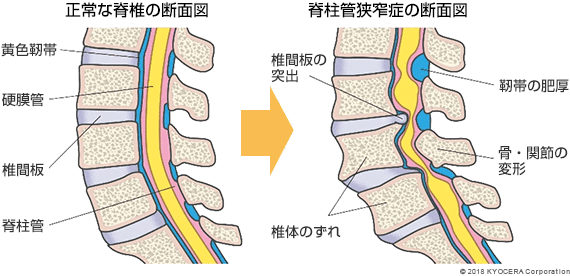
![]()
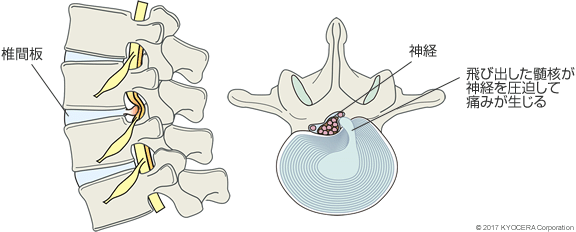
Q. 一般的な手術と低侵襲手術は、どのような違いがありますか?
A. 佐原先生:例えば腰椎椎間板ヘルニアの場合、神経の圧迫を取り除くために骨の一部を切除するのですが、一般的な手術では腰椎の後方まで見えるように皮膚を大きく切開して行います。同様のことを内視鏡を用いて行うと、小さな創で行うことができます。小さな創から金属の筒を挿入し、カメラで中を確認しながら手術を行います。
北口先生:創が大きいとその分、出血量が多くなり、骨から筋肉を剥離することで筋肉が萎縮することもあります。筋肉が少なくなると腰椎の安定性がなくなり、手術後に腰痛が続くこともあり、場合によっては再手術が必要になるケースもあります。
しかし、創が小さければ出血や筋肉のダメージも少ないので、身体にかかる負担を抑えられます。内視鏡手術の場合は再手術になる割合も低く、術後に腰痛を訴えられる方はほとんどおられない印象です。
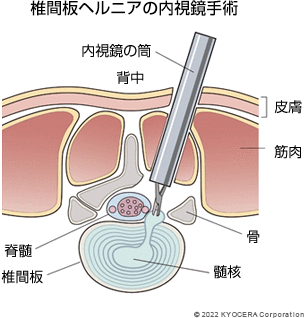
Q. 内視鏡を使った低侵襲手術は、どこの病院でも受けられますか?
A. 北口先生:内視鏡を用いてヘルニアを取る手術が行われるようになったのは10年ぐらい前です。しかし、内視鏡を導入していない病院は未だに多く、低侵襲手術は広く一般的に行われているとはいえない状況です。
当院では当初、腰椎椎間板ヘルニアの手術に内視鏡を取り入れ、内視鏡技術の進歩によって進入した逆側の圧迫も解除できるようになったことで、腰部脊柱管狭窄症の手術にも応用するようになりました。
佐原先生:術者としては、皮膚を大きく切開して広い視野を確保できるほうが手術はやりやすいので、小さな創で手術を行うには一定の経験と技術が必要になります。
Q. 内視鏡手術は進歩していますか?
 A. 北口先生:内視鏡手術は、かつては椎間板ヘルニアを対象として、約16mmの筒を使用するMED(micro endoscopic descectomy:内視鏡下腰椎椎間板摘出術)システムが主流でしたが、近年では腰部脊柱管狭窄症も治療対象として広がりを見せています。さらに、より低侵襲な手術であるFESS(full-endoscopic spine surgery:完全内視鏡下脊椎手術)へと進化し、現在では5〜8mmの2か所の小切開を用いて内視鏡手術を行うUBE(unilateral biportal endoscopy:片側進入双孔式内視鏡手術)という術式がアジアを中心に広がり、日本国内でも導入が進んでいます。
A. 北口先生:内視鏡手術は、かつては椎間板ヘルニアを対象として、約16mmの筒を使用するMED(micro endoscopic descectomy:内視鏡下腰椎椎間板摘出術)システムが主流でしたが、近年では腰部脊柱管狭窄症も治療対象として広がりを見せています。さらに、より低侵襲な手術であるFESS(full-endoscopic spine surgery:完全内視鏡下脊椎手術)へと進化し、現在では5〜8mmの2か所の小切開を用いて内視鏡手術を行うUBE(unilateral biportal endoscopy:片側進入双孔式内視鏡手術)という術式がアジアを中心に広がり、日本国内でも導入が進んでいます。
当院ではMEDシステムを基本としつつ、症例に応じてFESSによる手術も行っております。今後は、より幅広い症例に対応できるよう、UBEの導入も視野に入れて準備を進めているところです。
Q. 内視鏡手術において工夫されていることはありますか?
A. 北口先生:できるだけ骨や筋肉にダメージを与えないように手術を行っています。腰椎に変形がある場合は、より的確に処置できるようにナビゲーションシステムを使うこともあります。ただし、手術は侵襲が小さければよいというものではなく、手術リスクを抑えて安全に行うことが第一だと考えています。
佐原先生:神経を扱う脊椎外科の手術は、特に高い安全性が求められます。そのため症例によっては、麻酔が効いている患者さんの神経を術中にモニタリングする装置を使い、神経の状態をリアルタイムで確認しながら慎重に手術を進めています。
Q. ほかに手術において、低侵襲になっている面はありますか?
A. 北口先生:背骨の固定が必要な手術の場合、以前は骨から筋肉を剥離してスクリューを入れて固定していました。しかし現在は、小さな切開からスクリューを入れてロッドで固定するという経皮的(皮膚に小さな切開を加えて行う)な脊椎固定術を行っています。
Q. 骨が弱い患者さんだと、骨を固定する手術は大変そうな印象です。
 A. 佐原先生:骨がもろくなっている骨粗しょう症の患者さんの場合は、脊椎固定術が困難になることがあります。スクリューなどのインプラントがゆるんでしまうことで、固定部分でのトラブルが生じることもあります。そのため術前に骨の状態を評価し、必要があれば骨粗しょう症薬を使用することもあります。
A. 佐原先生:骨がもろくなっている骨粗しょう症の患者さんの場合は、脊椎固定術が困難になることがあります。スクリューなどのインプラントがゆるんでしまうことで、固定部分でのトラブルが生じることもあります。そのため術前に骨の状態を評価し、必要があれば骨粗しょう症薬を使用することもあります。
骨粗しょう症は、とにかく早期に診断を受けて治療をしておくことが大切です。というのも、背骨の骨折の中で最も多い圧迫骨折は主に骨粗しょう症によって起きています。骨がもろいままだと、何度も骨折を繰り返す場合もあります。
Q. 骨粗しょう症を予防する方法を教えてください。
A. 北口先生:女性の場合は、50歳を過ぎると徐々に骨密度が下がっていく傾向があるので、定期的に計測しておくことが大切です。日常生活においては、ウォーキングのほか適度に日光を浴びること、ビタミンDを摂取することなどが骨粗しょう症の予防につながります。
また日本の骨粗しょう症の患者数は1,590万人と推定されていますが、治療を受けている人の割合は10%程度と低いといわれています。骨粗しょう症自体には症状が無く気づきにくいので、診断を受けて治療をすることが大切です。
Q. 脊椎疾患の治療において、先生方が心がけておられることを教えてください。
A. 北口先生:第一に心がけているのは、安全に手術をすることです。低侵襲な手術を行うことは、その次です。低侵襲な手術を選択するよりも、より高い治療効果が期待できる場合は、侵襲が大きい術式を選択することもあります。
佐原先生:患者さんが何に困っておられるのかを見きわめて、治療にあたることを心がけています。当院では、紹介を受けて手術を前提に受診される方が大半ですが、例えば、腰椎椎間板ヘルニアの場合は手術が必要ではないケースのほうが多いです。基本となるのはあくまでも薬などを使った保存的な治療で、自然に症状が落ち着いてくることもあります。
Q. ありがとうございました。最後に先生方が医師を志されたエピソードを教えてください。
A. 北口先生:子どもの頃に「振り返れば奴がいる」というドラマを見て、「手術が上手い医者ってカッコいい」と憧れたことがきっかけです。
佐原先生:私はスポーツが好きで、子どもの頃は選手になりたいと思っていました。それが難しいと悟ったときに、選手をサポートできる職業に就きたいと思って整形外科医を目指しました。中でも脊椎外科を選んだのは、手術方法が多種多様にあって、カンファレンスを通してその患者さんにとってベストな手術法を模索していくことにやりがいを感じたからです。
取材日:2024.12.2
*本文、および動画で述べられている内容は医師個人の見解であり、特定の製品等の推奨、効能効果や安全性等の保証をするものではありません。また、内容が必ずしも全ての方にあてはまるわけではありませんので詳しくは主治医にご相談ください。


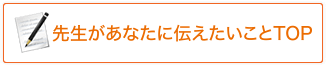
先生からのメッセージ
脊椎の手術に内視鏡を取り入れ、できるだけ身体への負担がかからない方法で手術を行っています。(北口 和真先生)
内視鏡を使った低侵襲手術は身体へのダメージが少ない分、入院期間が短いこともメリットです。(佐原 啓太先生)