先生があなたに伝えたいこと
【李 相亮・岡本 怜士・入内島 崇紀】骨折の予防には運動して筋力を鍛えることや、しっかりと栄養をとること、骨粗しょう症の治療をしていくことが大切です。
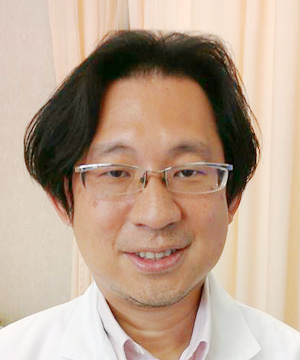
医療法人慶仁会 城山病院
り そうりょう
李 相亮 先生
専門:股関節・骨折・骨粗しょう症
李先生の一面
1.最近気になることは何ですか?
もともと若い頃は痩せ型だったのですが、最近は太ってきていて、体重を落とすためにジムに通っています。月に一度ぐらいしか行けていないので、もう少し頑張りたいと思っているところです。
2.休日には何をして過ごしますか?
現在、単身赴任をしており、週末は家族のいる東京へ帰っています。子どもがまだ小さいのですが、普段はあまり会えないので、帰ったときはめいっぱい子どもと一緒に公園などで遊んでいます。
このインタビュー記事は、リモート取材で編集しています。
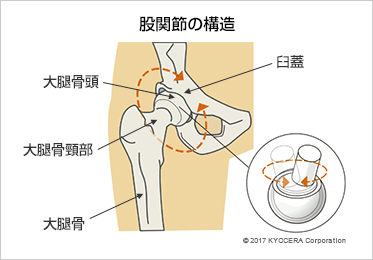 Q. まずは李先生にお聞きします。股関節の構造について教えてください。
Q. まずは李先生にお聞きします。股関節の構造について教えてください。
A. 股関節は骨盤側に臼蓋(きゅうがい)という受け皿があり、そこに大腿骨側の大腿骨頭(だいたいこっとう)が組み合わさっています。ボールとソケットの関係になっていて、球関節と呼ばれています。臼蓋も大腿骨頭も表面が軟骨で覆われているため、滑らかに動かすことができます。
Q. 股関節におけるケガについて教えてください。
A. 代表的なケガは、高齢の方に多く見られる大腿骨頸部骨折(だいたいこつけいぶこっせつ)です。骨がもろくなる骨粗しょう症のある方が、転倒で大腿骨の頸部を骨折してしまうことが多いです。
Q. 骨粗しょう症がベースにあるのですね。
A. 骨粗しょう症は現在、国内で約1,590万人の患者がいるといわれ、高血圧患者より少なく、糖尿病患者より多いといわれています。骨がもろいだけで症状がないため、未診断・未治療の方も少なくなく、ケガで受診して骨密度を測って初めて骨粗しょう症だとわかる、あるいは健康診断などでわかる方もおられます。現在、80代の方の半数以上は骨粗しょう症だといわれています。
骨がもろくなっている箇所で骨折が起こりやすいので、大腿骨頸部骨折の患者さんには、治療した後も次の骨折を起こさないように気をつけていただいています。
Q. 一度骨折を起こすと繰り返しやすいのですか?
A. よく「骨折の連鎖」といわれ、1度起こすと2~3度繰り返すことが多いです。大腿骨頸部骨折・転子部骨折(てんしぶこっせつ)を含む大腿骨近位部骨折(脚の付け根部分の骨折の総称)は、骨折後1年以内にもう片側の脚も骨折する人が非常に多く、背骨でも同様に連続で起こすケースが多いです。そのため、そうした骨折が見つかったら必ず骨粗しょう症の治療を始め、次の骨折を防ぐことが重要です。
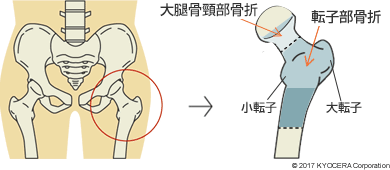
Q. 大腿骨近位部骨折の治療法について教えてください。
A. 基本的には、手術以外で治す方法はあまり推奨されていません。例えば頸部における骨折で骨がずれてしまっていると自然に骨がくっつくことはなく、様子を見ているうちに寝たきり状態になって衰弱していくことがあります。そのため基本的に、骨をつなぐ手術や人工骨頭・人工股関節などに置き換える手術が推奨されます。
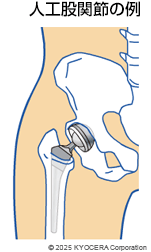
Q. 骨折の状態によって手術法が変わるのですか?
A. 大腿骨頸部骨折の場合は、血流が非常に乏しい股関節の中の部位の骨折なので、骨をつないでもくっつかない、あるいは骨壊死(こつえし)といって骨組織が死んでしまうこともあります。骨がずれていない場合は骨をつなぐ手術を行うこともありますが、ずれてしまっている場合は手術成績がよいといわれている人工骨頭あるいは人工股関節に置換する手術を主に行います。
Q. 骨折を起こさないためには、どのようなことに気をつければよいですか?
A. 骨折の予防には3本柱があります。1つは運動で、筋力が落ちると転倒しやすくなって骨折の原因になるので、筋力を鍛えることが大切です。高齢の方で介護保険をお持ちの方は、デイケアや通所・訪問リハビリなどの介護サービスを利用し、介護保険をお持ちでない方は整形外科クリニックや病院でリハビリを行うのがよいでしょう。2つ目は食事で、栄養を十分摂取すること。3つ目は、先にお伝えしたように骨粗しょう症の治療をすることです。
Q. 骨粗しょう症の治療法についても教えてください。
A. 基本的に薬物治療となり、今はたくさんの種類の薬があります。そもそも人間の体は絶えず骨を壊して作ることが繰り返され、それが均衡状態にあるとプラスマイナスゼロで骨は減りません。しかし、高齢になると女性ホルモンや男性ホルモンが減る影響で骨がどんどん壊されていく一方になり、作ることが追いつかない場合は骨粗しょう症になります。
そのため、薬物治療には、骨が減っていくのを止める骨吸収抑制作用を持つ薬剤や、骨を作る骨形成促進作用をもつ薬剤を使用します。骨吸収抑制剤は昔から用いられてきた薬ですが、最近は骨形成を高める薬も開発され、これらを使って骨を強くしていきます。
こうした薬物治療のほかにも、適度に日光に当たって散歩をすることで骨を強くすることも大切です。
Q. 続いて岡本先生にお聞きします。股関節における代表的な疾患である変形性股関節症の治療法について教えてください。
A. 患者さんの多くは、病院を受診すると手術を勧められると思われるようですが、いきなり手術ということは少なく、まずは生活スタイルなどをお聞きし、リハビリから始めていきます。股関節を傷めると関節が硬くなって動きが悪くなるので、リハビリでほぐしていきます。そうすると、それだけで痛みが軽くなる方もおられます。
それと同時に、痛みに応じた薬物治療や、股関節まわりの筋肉を鍛えるストレッチのような運動治療を行います。こうした保存的な治療を1~2カ月続け、効果がみられない場合に手術を検討します。
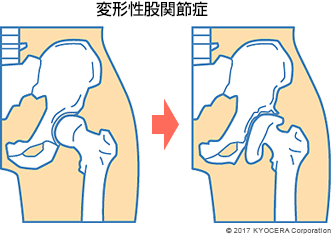
Q. どのような手術ですか?
A. 人工股関節置換術(じんこうこかんせつちかんじゅつ)です。変形性股関節症の患者さんは、臼蓋と大腿骨頭の軟骨が摩耗しているので、臼蓋を削ったり、大腿骨頭を切除したりして両方とも金属の人工物に置き換えます。臼蓋には半球状のカップ、大腿骨にはステムを打ち込んで、その間に軟骨の代わりになるポリエチレンライナーを挟みます。
この手術によって骨同士がぶつかることによる痛みが緩和されます。現在、人工関節は30年程度の耐久性が期待できるといわれています。
![]()
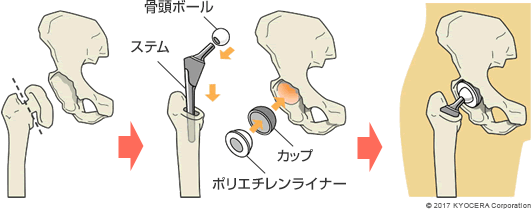
Q. 痛みがなくなるのは大きなメリットですね。
A. 変形性股関節症の患者さんは、歩行時の痛みもありますが、夜間痛で眠れない方が少なくありません。寝返りを打つと痛みで目が覚めるなど、生活が制限されるほどの痛みが手術によって改善されることが期待できます。「ぐっすり眠れるようになった」とか、痛みの辛さから化粧もされなかったような方が笑顔で外出されるようになったことをお聞きすると、あらためて除痛のメリットは大きいと感じます。
Q. 人工股関節置換術は以前よりも進歩しているのですか?
A. 昔は筋肉を切って手術していたので強い痛みがありましたが、現在は切開も10cm程度で、筋肉と筋肉の間から分け入って手術を行うので痛みも少ないです。筋肉を傷めることなく温存できるため、術後も筋力が発揮できてリハビリも進みやすくなっています。
また、以前は人工股関節置換術の合併症として脱臼のリスクがありましたが、筋肉を切らない手技が行われるようになってから、脱臼のリスクは低減されました。
Q. 人工関節置換術に使われるインプラントも進歩しているのですか?
A. 軟骨の役割を果たすポリエチレンライナーが改良され、摩耗しにくくなっているほか、ビタミンEが添加されて劣化しにくくなり、耐久性も上がっています。
また、ハイドロキシアパタイトがコーティングされたステムもあり、こちらは骨との固着が速く、かつ骨への刺激が少ないので痛みが減っているという報告もあります。このように、さまざまなインプラントが開発され、選択肢が広がっています。
 Q. 先生が手術において心がけていることを教えてください。
Q. 先生が手術において心がけていることを教えてください。
A. まずは患者さんが望まれる生活スタイルをお聞きして、さまざまなインプラントからその患者さんに合ったものを選ぶようにしています。先日は40代の方に人工股関節置換術を行いましたが、このあと何十年も使っていただくために様々な検討をしました。
世界的な医学雑誌では、20世紀で最も成功した手術の1つとして、人工関節置換術が挙げられています。インプラントや手術手技は目覚ましく進歩しているので痛みを我慢し続けるよりも早めに手術することを検討していただきたいと思っています。
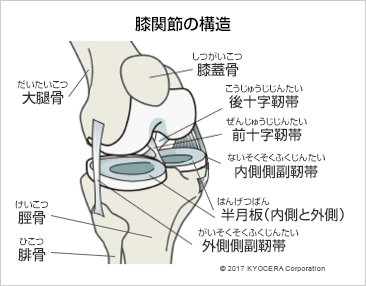 Q. 続いて入内島先生にお聞きします。膝関節の構造について教えてください。
Q. 続いて入内島先生にお聞きします。膝関節の構造について教えてください。
A. 膝関節は大腿骨と脛骨(けいこつ)から成る関節です。それぞれの骨の表面は軟骨で覆われ、骨と骨の間にはクッション材となる半月板(はんげつばん)があるほか、骨と骨をつなぐ靱帯(じんたい)があります。これらの組織が傷んでくると、痛みが出てきて治療が必要になります。
Q. 膝関節にはどのような疾患が多いですか?
A. 軟骨損傷、靱帯損傷、半月板損傷といったケガのほか、これらの組織が加齢に伴って傷み、骨が変形していく疾患として、変形性膝関節症(へんけいせいひざかんせつしょう)があります。ほかにも、関節リウマチや骨の中の血のめぐりが悪くなることにより発症する骨壊死などもあります。
変形性膝関節症は60代以降、特に女性の方に多くみられます。膝関節に長年の負担がかかることで発症する面もありますが、若いときに半月板や軟骨を傷めたために骨の変形が早く進むケースもあります。
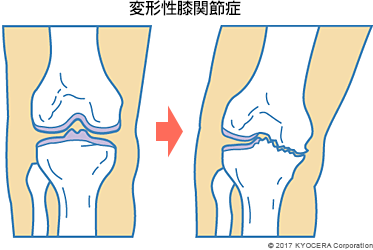
Q. 痛みについても教えてください。
A. ケガの場合はケガによる痛みが出ますが、変形性膝関節症が進んで軟骨がなくなってくると骨同士がぶつかり、日常的に痛みがあらわれます。歩行や階段の昇り降りも痛みで困難になることもあり、膝関節が変形して曲がらなくなり歩行ができなくなると、そこから体力と筋力が落ち、余計に膝関節の変形が進むという悪循環に陥ることもあります。
特に日本人は骨格の傾向と、正座など膝を曲げる生活習慣があることからO脚の人が多いです。しゃがんだりする動作によって膝関節の内側の軟骨がさらにすり減ってO脚が進み、変形が進むことがあります。
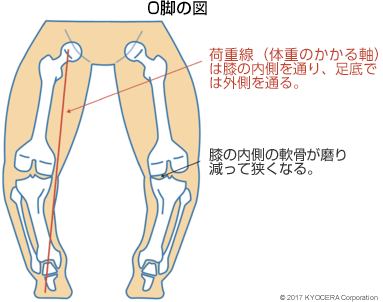
Q. どのように治療するのですか?
A. 軟骨損傷や半月板損傷の場合は、それらを整復する治療を行いますが、軟骨がなくなってしまっている場合は元に戻すことはできません。最初の2~3カ月は薬や運動などによる保存的な治療を行いますが、痛みが落ち着かない場合は人工膝関節置換術(じんこうひざかんせつちかんじゅつ)となります。
骨は歯と同じなので、虫歯で穴が開いている場合は虫歯を削って銀歯を被せるのと同様に、膝関節の場合も傷んだ軟骨や骨を削り取って金属を被せます。傷みが一部であれば、その箇所だけを置換する人工関節もありますし、すべてが傷んでいる場合は全部を置換するパターンもあります。また、そこまで必要がないほどの軽い損傷の場合は、骨を切ってバランスを調整する骨切り術(こつきりじゅつ)という手術もあります。
Q. 人工膝関節置換術はどのように行うのですか?
A. 患者さんの膝関節の大きさに合わせてインプラントを選び、傷んだ骨を削ってからインプラントを被せて人体用のセメントで固定します。インプラントの間には、軟骨の代わりになるポリエチレンを挟みます。痛みは骨の表面で感じるものなので、表面を金属に置換することで除痛が期待できます。またO脚などの場合も、まっすぐになるようにバランスを整えます。
![]()
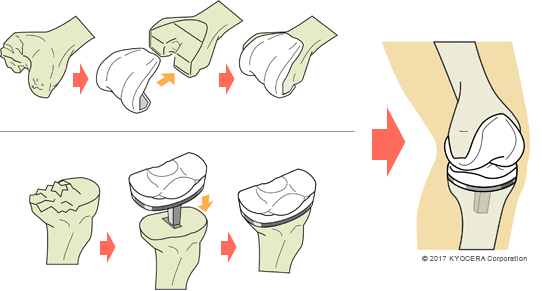
 Q. 人工膝関節置換術において進歩している面はありますか?
Q. 人工膝関節置換術において進歩している面はありますか?
A. インプラントの進歩が大きいと思います。以前よりも膝関節本来の動きに近い動きができるインプラントが開発されて膝関節の可動域が広くなり、より深く膝を曲げることができて安定感もあります。また、インプラントの長期成績もよくなってきています。
手技の面でも、数十年前に比べると切開の大きさも半分程度で、筋肉も傷めずに手術ができるようになりました。術後に安静が求められると寝たきりになって筋肉が落ちたり、褥そう(じょくそう:長時間の圧迫で生じる皮膚の損傷)ができたり、肺炎になったりなど、合併症が増えてしまいますが、現在は手術の翌日からリハビリができ、早期に退院できる方が多いです。
以前よりも身体への負担が少なくなっているので、買い物や旅行などに行けないなど、膝の痛みで生活が制限されている場合は、積極的な治療を検討することをお勧めしています。
Q. では李先生、手術の合併症についても教えてください。
A. 手術の合併症で最もリスクが高いのは、脚の静脈に血の塊ができる下肢静脈血栓症(かしじょうみゃくけっせんしょう)です。骨折をしてベッド上で寝たままになったり、手術後にあまり脚を動かさないでいると、脚の静脈に血の塊(血栓)ができ、それが血管の壁に貼りつきます。手術後にリハビリで歩くときなどに、その血栓が血管の壁からはがれてしまうことがあり、それが静脈を通って移動して肺の動脈を詰まらせてしまうことがあります。これを肺塞栓症(はいそくせんしょう)といい、肺動脈が血栓によりすべて詰まってしまった場合は窒息と同じ状態となり、命にかかわります。そうしたことが起こらないように、血栓予防薬という血液を固まりにくくする薬を使って予防をしています。
ほかには、感染や出血過多による貧血などもあります。人工関節置換術では、感染は1%前後の割合で起こるといわれ、対策としては手術前後に予防的に抗生剤を投与しています。また、手術時間が短いと感染の割合は低くなるため、できるだけ短時間で手術が終わるようにするとともに、手術では組織の血流をできるだけ温存するように心がけて予防に努めています。
Q. 大腿骨近位部骨折術後のリハビリについても教えてください。
A. 下肢機能の再獲得には、できるだけ早期にリハビリを行うことが非常に重要になります。当院では可能な限り入院から48時間以内に手術を行うことを目指しており、手術の翌日から立位訓練や歩行訓練を開始し、元の歩行能力を取り戻していくスケジュールで治療しています。
リハビリ期間は、患者さんの年齢や元の歩行能力にもよるので個人差がありますが、活動性が高くて筋力がある患者さんでは、2~3週間程度のリハビリ治療で自宅退院が可能となる方もおられますし、ご高齢で筋力が落ちている患者さんでは、3週間ぐらい当院でリハビリ治療してから回復期リハビリ病院に移って、2~3カ月間リハビリを続けてから自宅退院が可能となる方もおられます。
 Q. ありがとうございました。では最後に、先生が医師を志したきっかけを教えてください。
Q. ありがとうございました。では最後に、先生が医師を志したきっかけを教えてください。
A. 当院は、私が6歳の時に父が開院しました。幼い頃から父が働いている姿を見ていて、自分も人を助ける医師になりたいと思っていました。また、子供の頃に外科医が主人公の漫画を愛読し、その影響で外科系を志望し、整形外科を選びました。整形外科は歩行ができない方や痛みで苦しんでいる方が、手術で苦しみから解放されて、元の生活を取り戻すという結果に直結することが多い分野なので、非常にやりがいを感じています。
リモート取材日:2025.2.6
*本文、および動画で述べられている内容は医師個人の見解であり、特定の製品等の推奨、効能効果や安全性等の保証をするものではありません。また、内容が必ずしも全ての方にあてはまるわけではありませんので詳しくは主治医にご相談ください。




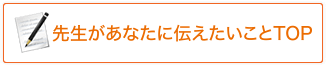
先生からのメッセージ
骨折の予防には運動して筋力を鍛えることや、しっかりと栄養をとること、骨粗しょう症の治療をしていくことが大切です。