先生があなたに伝えたいこと
【秋山 典宏】骨がもろくて起こる椎体骨折を防ぐことはもちろん、繰り返さないためにも骨粗しょう症の治療をすることが重要です。

三菱京都病院
あきやま のりひろ
秋山 典宏 先生
専門:脊椎脊髄
秋山先生の一面
1.最近気になることは何ですか?
勤務先の病院が転換期を迎えているため、どのように変わっていくのかが気になっています。脊椎の治療においては、手術の器械もどんどん進歩して治療方針も更新されていくので、この先も学び続けてよりよい治療に挑みたいです。
2.休日には何をして過ごしますか?
毎週金曜に手術をしているので、土曜は手術をした患者さんの処置のために病院に来ています。その後は、脊椎に関する勉強をしたり、学会や講演の準備をしたりなど、休日も仕事に関わることが多いです。時間があるときは、映画を観たり、カフェでコーヒーを飲みながら読書したりします。スポーツジムで運動することもあります。
このインタビュー記事は、リモート取材で編集しています。
Q. ご高齢の方に多くみられる椎体(ついたい)骨折について教えてください。
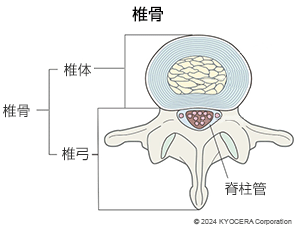 A. 脊椎(せきつい)は、円柱状の椎骨(ついこつ)が連なって構成されています。その椎骨の前方(腹部側)を椎体といい、そこが潰れるのが椎体骨折です。骨粗しょう症圧迫骨折とも呼ばれています。骨粗しょう症で骨がもろくなっていることで、通常は骨折しない程度のちょっとした衝撃で骨が潰れてしまいます。
A. 脊椎(せきつい)は、円柱状の椎骨(ついこつ)が連なって構成されています。その椎骨の前方(腹部側)を椎体といい、そこが潰れるのが椎体骨折です。骨粗しょう症圧迫骨折とも呼ばれています。骨粗しょう症で骨がもろくなっていることで、通常は骨折しない程度のちょっとした衝撃で骨が潰れてしまいます。
Q. 椎体骨折が起こりやすい場所はありますか?
A. 胸椎(きょうつい)は1番から12番までの椎骨があり、腰椎(ようつい)は1番から5番までの椎骨があります。胸腰移行部(胸椎から腰椎に移行する部分)の胸椎11、12番や腰椎の1、2番に骨折が多くみられます。もちろん衝撃の加わり方やその方の体型などによって、胸椎の1~10番や腰椎の3~5番が潰れることもあります。
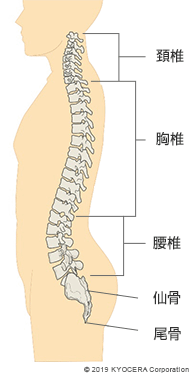
 Q. どのような方に起こりやすいですか?
Q. どのような方に起こりやすいですか?
A. 骨粗しょう症になりやすい方や、高齢の女性で瘦せ型の方が多いです。また、生活習慣病とされる糖尿病や慢性腎不全、慢性閉塞性肺疾患(まんせいへいそくせいはいしっかん)を持っておられる方にもよくみられます。グルココルチボイド誘発性骨粗しょう症といって、ステロイド剤を使用することで骨がもろくなっている方も起こりやすいです。ほかにも飲酒や喫煙なども関係しています。
単に骨密度が低いから椎体骨折を起こしやすいというだけでなく、骨質(こつしつ)も骨の強度に関係しています。糖尿病の患者さんなどは、骨質が悪くて椎体が潰れやすいことがあります。
Q. 椎体骨折は「いつのまにか骨折」などとも呼ばれますよね?
A. 例えば尻もちをついたり、つまずいて転倒したり、重いものを持ったりしたときに特に症状が出なくても、骨に細かい傷が入っていて徐々に潰れていくことがあります。あるいは日常生活の動作による負荷の積み重ねや、ご本人の体重がかかることでいつのまにか潰れるケースもあります。痛みを自覚していないのに、レントゲン検査をすると骨折が判明するということも珍しくありません。
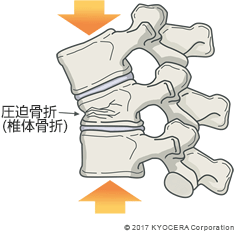
Q. 骨折に気づかないまま時間が経過するとどうなりますか?
A. 後弯変形(こうわんへんけい)といって背骨が曲がって、前傾姿勢になることが多いです。そうすると体を支えるのが辛くなって、歩行時に負担がかかります。歩きにくくなると、家に閉じこもりがちになって運動量が減り、筋力が落ちれば骨量も相対的に減っていきがちです。さらに、背骨にかかる力学的な問題でさらなる骨折を起こしやすく、悪循環することがあります。また、前傾姿勢によって消化器官が圧迫され、逆流性食道炎を起こすことがあるなど、内臓への影響が出ることもあります。
Q. 椎体骨折の診断はどのように行うのですか?
A. 骨折は基本的にレントゲン検査で診断しますが、椎体骨折の初期の段階ではレントゲン検査ではわからないケースもあります。そのため、椎体骨折が疑われる場合にはCTやMRI検査を行うこともあります。
Q. 治療方針についても教えてください。
A. 保存治療が原則となり、骨粗しょう症の治療をしていない場合はすぐに開始します。日常生活ができるようであればコルセットを着けていただいて、しばらくは安静にしながら骨がくっつくのを待ちます。ただし、痛みが強くて動けない、あるいは骨が潰れている範囲が広く、足のしびれなどの神経症状が出ている場合は手術的な治療が必要になります。
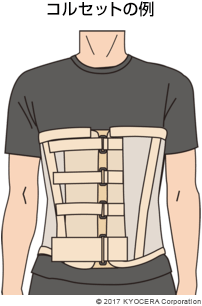
Q. 手術はどのようなものですか?
A. 一般的に行われるのは、潰れた椎体内に骨セメントを入れて固めるBKP(経皮的椎体形成術)です。椎体に細い管を通して風船のような器械を入れて中で膨らませ、整復されてできた空洞に骨セメントを注入して固めます。骨セメントだけでは支えられない場合は、金属のスクリューを入れて固定する場合もあります。崩れそうになっている家を支えるために補強工事をするようなイメージです。骨セメントを入れてスクリューで固定しても、骨が極度にもろい場合はそれが抜けてくることもあるので、スクリュー自体を骨セメントで固め、より強固にすることもあります。
![]()
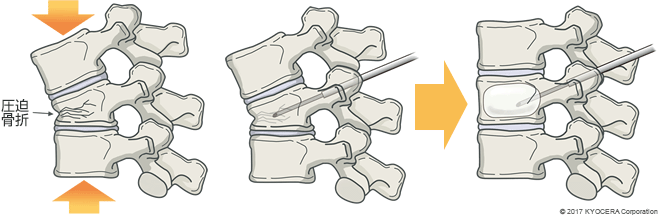
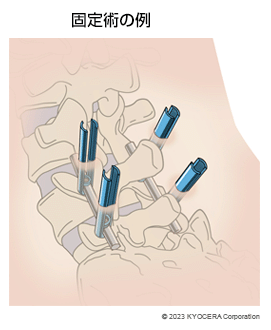
さらに、椎体の潰れ方によっては脊髄や馬尾(ばび)神経などが圧迫されて神経症状が出ている場合もあるので、そのようなときは神経の圧迫を取る除圧術(じょあつじゅつ)が必要になることもあります。
また、潰れている箇所が複数の場合もあり、広い範囲を固定することもあります。患者さんによって椎骨の並び方や脊椎のカーブも異なるので、矯正が必要になる場合もあり、2~3度に分けて手術を行うこともあります。
Q. 術後のリハビリについても教えてください。
A. 手術の1~3日後から立って歩く練習を始めます。もともと活動性のあった方は、1カ月以内で退院されることが多いですが、そうでなかった方は回復期病院や地域包括病院などに転院してリハビリを続けられることが多いです。
Q. 退院後に気をつけるべきことはありますか?
A. 椎体骨折は2次骨折に気をつけなければならないので、引き続き骨粗しょう症の治療を続けることが重要です。折れた骨が自然にくっついた場合は、硬くなって固まるのでその場所は折れにくいですが、まわりの骨はもろいままなので骨折を起こした箇所のすぐ近くがまた骨折することがあります。特に椎体骨折を起こしてから数カ月間は、次の骨折が起こる可能性が高まります。そのため、術後半年ほどはコルセットをつけていただき、骨粗しょう症の薬を欠かさず服用しながら定期的に受診することが大切です。
Q. そもそも椎体骨折が起こらないように予防するには、何が大切ですか?
A. まずは骨粗しょう症の検査をすることです。骨粗しょう症だと分かればすぐに服薬の治療を始めることができ、椎体骨折の予防につながります。骨密度が下がりきってしまうと改善するのが難しくなりますが、早めに治療を始めると回復しやすく、比較的高い骨密度を維持しやすい傾向があります。
また、骨粗しょう症の診断を受ければ、日常生活において転倒したり腰に負担がかかったりしないようにご自身で注意することもでき、危険回避につながります。50歳を過ぎれば骨密度の検査を受けることが推奨されていますが、女性の方は40歳を過ぎればぜひ一度検査して、ご自身の骨密度を把握しておいていただきたいです。
 Q. ありがとうございました。では最後に、先生が脊椎脊髄を専門にされた理由を教えてください。
Q. ありがとうございました。では最後に、先生が脊椎脊髄を専門にされた理由を教えてください。
A. 最初は研修医として整形外科に入局して整形外科全般を学んだ後、脊椎外科のある病院に赴任したことを機に、この分野に興味を持ちました。脊椎外科において、骨粗しょう症による椎体骨折は非常に多いのですが、手術をして治ってもまたまわりの骨が潰れて手術になることも少なくありません。そのため私は、治療の難易度が高い3大疾患の一つと捉えて取り組んでいます。骨がボロボロになってしまうと、どれだけ工夫して補強しても追いつかず、骨そのものが強くならなければ骨折を繰り返してしまいます。だからこそ、骨粗しょう症の早期治療の大切さを広く知っていただきたいと思っています。
リモート取材日:2024.9.26
*本文、および動画で述べられている内容は医師個人の見解であり、特定の製品等の推奨、効能効果や安全性等の保証をするものではありません。また、内容が必ずしも全ての方にあてはまるわけではありませんので詳しくは主治医にご相談ください。


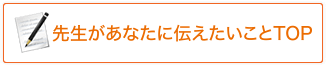
先生からのメッセージ
骨がもろくて起こる椎体骨折を防ぐことはもちろん、繰り返さないためにも骨粗しょう症の治療をすることが重要です。