先生があなたに伝えたいこと
【隈元 真志】痛みやしびれ、歩きにくさなど、お困りごとを丁寧にお聞きし、患者さんそれぞれに合った治療をご提供します。【津田 圭一】的確な診断と適切な治療を心がけて、症状の改善を目指します。

福岡脊椎クリニック
くまもと しんじ
隈元 真志 先生
専門:脊椎脊髄
隈元先生の一面
1.最近気になることは何ですか?
クリニックを開業して1年が経ちますが、治療だけでなく予防の取り組みもできないかと検討しています。早期に受診していただくための啓発活動や運動講座などができたらと思案中です。
2.休日には何をして過ごしますか?
ランニングが好きなので、以前はフルマラソン出場に向けてよく走ったりしていました。けれども最近は、娘たちの習いごとの発表会を観に行く機会のほうが多いです。

福岡脊椎クリニック
つだ けいいち
津田 圭一 先生
専門:脊椎脊髄
津田先生の一面
1.最近気になることは何ですか?
尊敬する先生が学会で「美しく老いる」をテーマに掲げておられ、自身も疲れやすくなってきたこともあり、アンチエイジングに関心を持っています。情報を収集し、患者さんにも助言できたらと思っています。
2.休日には何をして過ごしますか?
私は長崎県出身で、1~2年ほど前に家族と一緒に福岡県に移り住みました。まだこの地域のことをよく知らないので、休日は散策に出かけたりして新しい発見を楽しんでいます。
Q. 脊椎の疾患には、どのようなものがありますか?
A. 隈元先生:脊椎の中を通る神経に腫瘍ができたり、細菌感染したりする病気もありますが、一般的に多くみられるのは脊椎の変性による疾患です。高齢になると難聴や老視になりやすいのと同様に、脊椎においても背骨や周辺組織が傷んできます。背骨が変形したり、組織が突出・肥厚したりすることで、背骨の中の神経にまで影響が及び、痛みやしびれなど、様々な症状が現れます。
津田先生:来院される患者さんの主訴で一番多いのは「腰痛」です。我々は、それがどのような疾患から引き起こされているのかを的確に診断しながら見極めます。神経が圧迫されることで痛みを引き起こす疾患として、腰部脊柱管狭窄症(ようぶせきちゅうかんきょうさくしょう)や椎間板(ついかんばん)ヘルニアがあります。このほかにも、例えばスポーツによって椎間板を損傷している、あるいは腰椎分離症といって疲労骨折によって腰椎が分離しているなど、腰痛の原因は多岐にわたります。
![]()
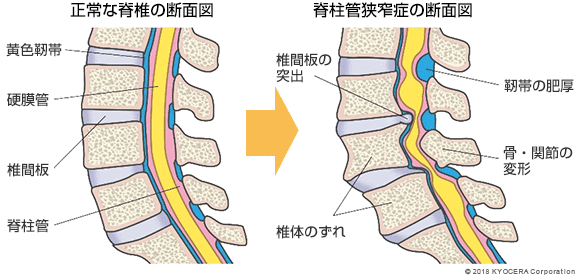
![]()
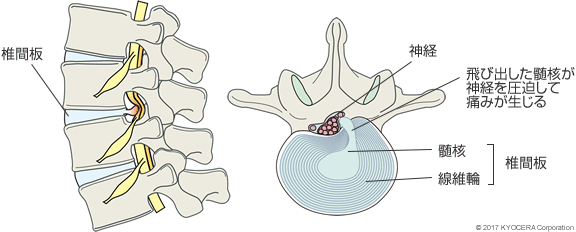
Q. 患者さんは、病院に行くべきか迷われるケースもあるかと思います。受診の目安を教えてください。
A. 隈元先生:体に力が入りにくいといった症状があれば早めに受診していただければと思います。神経には、運動を司る神経と感覚を司る神経があり、一般的に神経が圧迫されると感覚神経のほうから先に症状が現れ、次第に運動神経にも症状が現れます。そこまで進行してしまうと、筋肉がうまく動かせなくなって筋肉が痩せていき、日常動作を行うことが難しくなることもあります。
早めに受診していただければ進行を抑えられる可能性が高まりますので、「年のせいだから仕方がない」とあきらめてしまわずに、こういった症状があれば医療機関へ相談に行くことをお勧めします。
津田先生:患者さんは、テレビや雑誌、インターネットなどの情報から、病気とご自身の症状を照らし合わせ、受診されるケースが多いと思います。ただし、この症状だからこの病気だろうと予想されていても、実際に我々が診ると違う場合もあります。適切な治療を受けるためにも、情報だけで判断せずに早めに受診していただくことが大切だと思います。
 Q. どのように診断するのですか?
Q. どのように診断するのですか?
A. 隈元先生:目の前の患者さんの症状と、レントゲン検査、MRIやCTなどの検査画像、これまで数々の疾患を診てきた専門医としての経験を照らし合わせて診断を行います。背骨由来の症状ではない可能性があれば、背骨の神経の根元にある神経根にブロック注射を行うことによって、症状が改善されるかを確かめます。それで改善されない場合は、背骨由来の症状ではないということになりますので、別の科の医師につなぎます。
津田先生:一概に腰部脊柱管狭窄症や椎間板ヘルニアといっても、患者さんの状態は様々で、どの部分に問題があるのかを慎重に見極めなければなりません。単に脚のしびれがあるからしびれの薬を処方するというのではなく、より細かく診断をして症状の改善につなげたいと考えています。
Q. 治療法についても教えてください。
A. 津田先生:椎間板ヘルニアは、以前はすぐに手術治療を行うケースもありましたが、最近は自然に治る方もおられ、保存治療で様子を見るケースも増えてきています。ヘルニアは椎間板が飛び出ていることで症状をもたらしますが、それが引っ込むと痛みやしびれも軽くなります。痛みが強く、歩行が困難なほど重度の場合は、手術を行うことが多いですが、そこまで至っていない場合は、症状が強く出る時期に痛み止めの薬やブロック注射、点滴などで症状を抑えることもあります。
腰部脊柱管狭窄症も同様に、寝ている時は問題がなく、歩行時にのみ両足がしびれる馬尾(ばび)症状がある場合は、薬で歩行時の症状を抑えることがあります。椎間板ヘルニアや腰部脊柱管狭窄症は、加齢に伴って少しずつ進行していく傾向がある変性疾患です。そのため薬などの保存治療を行いながら、生活に支障が出てくると手術をご提案することもあります。
Q. どのような手術ですか?
A. 隈元先生:神経の圧迫を取り除くための除圧術が一般的な手術となります。神経を圧迫するものが骨であれば骨を削り、ヘルニアであればヘルニアを切除します。さらに、背骨がぐらついていたり、骨の変形が強くなっていたりする場合は、安定させるために骨同士をボルトで固定する固定術や矯正なども行います。
こうした除圧や固定の手術をできるだけ患者さんの身体に負担がかからないように行う脊椎内視鏡手術もあります。細い機器による小さな切開で手術を行うため、身体への負担がかなり小さい手術となります。また、切開が小さいため、内視鏡手術は術後の回復が早くなることが期待できます。
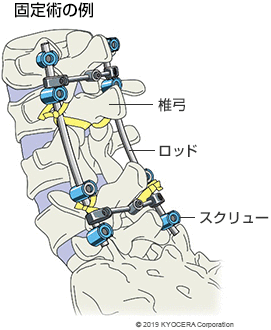
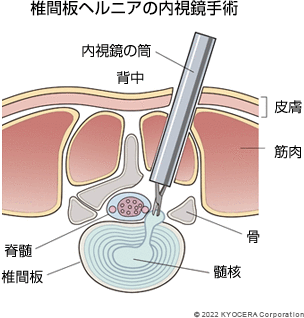
Q. 矯正を伴う手術も内視鏡でできるのですか?
A. 隈元先生:矯正する範囲によります。内視鏡は特定の場所を手術することには長けていますが、範囲が広くなると難しいです。変形の範囲が広くなる前に診断を受けていただければ、身体への負担が小さい手術で治療ができる可能性が高まるかと思います。
津田先生:脊椎に使える内視鏡は、現在3種類あります。いずれも筒状の機器なので、奥までピンポイントで届くことがメリットです。特に肥満の強い方は、従来の手術法だと脊椎部を目視するために大きく切開する必要があり、術後の負担が大きかったのですが、内視鏡手術だと小さな切開で手術ができます。
ただし万能な手術とはいえません。ヘルニアを取る手術などには向いていますが、隈元先生がお話しされたように広い範囲にわたる脊柱管狭窄症などには適用できないこともあります。
 Q. 手術の合併症についても教えてください。
Q. 手術の合併症についても教えてください。
A. 隈元先生:一般的な合併症として、出血や神経の損傷、感染などがあります。特に皮膚を大きく切開する手術の場合は、出血量が多くなるリスクがあります。一方で、内視鏡手術は創の中に血だまりが起こりやすいほか、生理食塩水を流し込みながら手術を行うため、硬膜(こうまく:脊髄を覆う膜)が見えにくくなり、誤って損傷させてしまう可能性もあります。また、固定術の場合は、ボルトで固定した部分としていない部分との骨の強度のバランスが合わず、ヘルニアや骨折を起こしてしまうこともあります。
津田先生:近年は、こうした合併症を防ぐ技術の進歩が著しいです。例えば、患者さんごとに異なる骨の形状に合わせ、どこをどう削ればよいかを1mm単位でナビゲーションできるシステムや、術中に神経の状態を確認する脊髄モニタリングなどがあります。また、内視鏡のカメラの画像解像度もかなり上がっています。もちろん、我々医師が確かな技術を身につけていることも、安全性の高い手術のために重要だと思います。
Q. 術後の入院期間、リハビリ内容についても教えてください。
A. 隈元先生:内視鏡手術で約1週間、従来型の手術で約2週間程度が目安となりますが、入院期間を決めるのはあくまでも患者さんです。患者さんが望むことや術後の状態などはお一人おひとり違いますので、入院期間やリハビリ内容も異なります。特に日常生活の動作機能を取り戻すためのリハビリは重要で、それぞれの課題に応じて、退院後も外来のリハビリに通うケースが多く見られます。リハビリ期間中は、理学療法士さんや作業療法士さんのもとで訓練を続けていただきます。
津田先生:日常生活で階段の上り下りをされる方で、脚の筋力が落ちている方、マヒのある方は、特に筋力を回復させるリハビリが必要になります。私がリハビリに関して患者さんによく話すのは、歯のケアと同じだということです。歯の治療を終えてからも虫歯にならないように歯磨きするのと同じように、腰痛にならないようにリハビリを続けることが大切です。術後のリハビリが終了すればおしまいではなく、継続してトレーニングを行っていただきたいです。
 Q. ありがとうございます。では、先生方が脊椎を専門とされたきっかけを教えてください。
Q. ありがとうございます。では、先生方が脊椎を専門とされたきっかけを教えてください。
A. 隈元先生:もともとは脳外科医として、主に脳卒中の患者さんを診療していましたが、脊椎疾患の研修会への参加を機に脊椎の専門医になりました。そこで、脊椎疾患で行動を制限されていた患者さんが治療を経て元気になっていく姿を見て、治療の成果を感じました。さらに、手術をすればおしまいではなく、患者さんとのお付き合いが長く続くことにも魅力を感じました。
津田先生:医師になって2年目ぐらいのとき、パラグライダーで墜落して骨折された患者さんが手術によって見事に回復されたのを目の当たりにしました。その患者さんがまたパラグライダーを再開されたという話を聞いて、脊椎診療に大きな魅力を感じたことが専門医になるきっかけになりました。
 Q. 最後に、治療において先生方が心がけておられることを教えてください。
Q. 最後に、治療において先生方が心がけておられることを教えてください。
A. 隈元先生:患者さんの仕事や日常生活、やりたいことにおいて、どのようなことで困っているのかを聞き出し、治療によって改善することを心がけています。ご家族のサポートがあるのかも含めて、患者さんお一人おひとりが抱えておられる悩みは様々です。そうした生活背景を想像しながら目指すゴールを設定し、治療をご提案しています。
津田先生:「蝶のように舞い、蜂のように刺す」という診療を目指しています。これは専門医として的確な診断のうえに適切な治療をすることだと思っていて、結果的に患者さんのADL(日常生活動作)やQOL(生活の質)の向上につながると思います。
取材日:2025.5.21
*本文、および動画で述べられている内容は医師個人の見解であり、特定の製品等の推奨、効能効果や安全性等の保証をするものではありません。また、内容が必ずしも全ての方にあてはまるわけではありませんので詳しくは主治医にご相談ください。


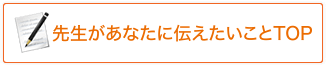
先生からのメッセージ
痛みやしびれ、歩きにくさなど、お困りごとを丁寧にお聞きし、患者さんそれぞれに合った治療をご提供します。(隈元 真志先生)
的確な診断と適切な治療を心がけて、症状の改善を目指します。(津田 圭一先生)