先生があなたに伝えたいこと
【青山 正寛】椎体骨折は、早期に診断を受けると、身体への負担が小さい方法で治療ができる可能性が高まります。
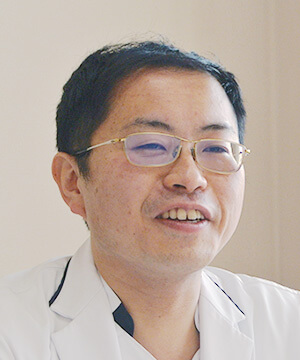
津島市民病院
あおやま まさひろ
青山 正寛 先生
専門:脊椎脊髄
青山先生の一面
1.最近気になることは何ですか?
いつも患者さんに食事や運動の大切さをお話しているので、最近は自分でも気をつけています。昨年は8kg太ってしまったのですが、自炊して運動をすることで体重を戻すことができたので継続しています。
2.休日には何をして過ごしますか?
旅行が趣味なので、長期休暇のたびにあちこちを旅行しています。今は九州全土をまわりたいと思っているので、昨年の鹿児島、宮崎、長崎に続き、今年は熊本に行く計画を立てようと思っています。
このインタビュー記事は、リモート取材で編集しています。
Q. 最近よく耳にする椎体(ついたい)骨折について教えてください。
A. 骨の強度が低下している骨粗しょう症の方によく起こる骨折です。背骨は、椎骨(ついこつ)の連なりでできていて、お腹側にある椎体(ついたい)と背中側にある椎弓(ついきゅう)から構成されています。骨粗しょう症の方は、椎体が折れることが多いです。
また背骨は、頚椎(けいつい)、胸椎(きょうつい)、腰椎(ようつい)と分けられますが、胸椎から腰椎に移行する胸腰移行部で起こることが最も多いといわれています。
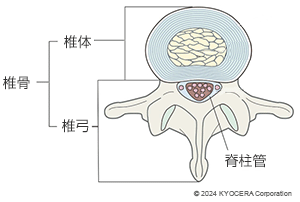
Q. どのようにして骨折することが多いですか?
A. 高い場所や階段から落ちたり、交通事故に遭ったりというほかに、ご高齢の方は転倒して尻もちをついて起こることも多いです。ほかにも、くしゃみをしたり、腰をひねったり、重いものを持ち上げたりなどでも発生することがあります。最近は、ご本人がまったく気づかないうちに骨折が起きていたというケースも多くみられます。
もちろん痛みが出れば気づくものですが、もともと骨粗しょう症がある方には、日常生活で直立歩行する中で体重が背骨にかかる負荷によって徐々に骨が変形して折れるという「いつのまにか骨折」という形態もあります。
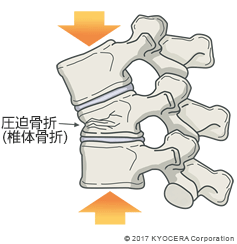
Q. 複数の骨折が起こる場合もありますか?
A. 背骨全体が弱くなっている場合は、隣り合う椎骨がドミノ倒しのように何カ所かにわたって折れる「ドミノ骨折」が起こることもあります。この場合でも、痛みがなくて骨折したことに気づかれない方もおられます。
Q. 気づかないまま時間が経過するとどうなりますか?
A. 骨折の箇所が多いほど、身長が低くなるほか背骨が曲がって猫背になります。そうすると肺が圧迫されて肺活量が落ちたり、胃が圧迫されて食欲が落ちたりなど、内臓機能が衰え、活動性が低下して最終的には寝たきりの原因になってしまう可能性もあります。
また、骨折の仕方によっては神経を圧迫して脚の機能に影響をもたらすこともあります。椎体の後ろには脊髄から馬尾神経(ばびしんけい)が通っていますが、骨折した骨が飛び出てその神経を圧迫すると、脚に運動マヒや感覚障害をきたすことがあります。
 Q. 椎体骨折の診断方法について教えてください。
Q. 椎体骨折の診断方法について教えてください。
A. まずはレントゲン検査を行いますが、非常に軽微な骨折の場合は背骨の形状に全く変化が現れないこともあります。その場合はMRI検査を行うこともあります。MRIは変形がない椎体骨折も的確に診断することができ、先ほど言った神経の圧迫なども同時に診断できます。レントゲン画像で異常が見られなくても痛みが続いている場合は、骨折が隠れている可能性があるのでMRI検査をすることをお勧めします。
Q. 椎体骨折の患者さんは増加傾向にありますか?
A. 高齢化社会の中、非常に増えています。骨粗しょう症が背景にあることから、閉経後にホルモンバランスが崩れた女性に多くみられますが、もちろん男性の患者さんもおられます。骨粗しょう症にならないことが椎体骨折の予防につながります。
Q. 骨粗しょう症はどのようにすれば予防できますか?
A. 食事と運動が大切です。骨を作るためのカルシウムが取れる牛乳やチーズなどの乳製品、カルシウムの吸収を促進させるビタミンDが取れるサケやサンマ、しいたけ、卵などをバランスよく食べることが大切です。運動においては、身体に振動を与えることで骨が刺激されて骨が強くなるということが最近分かっています。急に強い運動負荷をかけるのではなく、散歩などのほか、エスカレーターではなく階段を使うことなどから取り組まれるとよいと思います。それによって脚の筋力も育まれ、転倒の防止にもつながります。
Q. 食事と運動で骨の強度が上がれば、骨折予防につながるのですね。
A. 骨粗しょう症の予防をしながら、定期的な検査でご自身の骨密度を把握しておくことも大切です。最近は自治体の健診でも骨密度検査が受けられる機会が増えているようなので、積極的に活用していただきたいです。
Q. 骨粗しょう症と診断された場合は、どのような治療が必要ですか?
A. 内服薬や注射製剤などで骨密度を高めていく治療になります。以前に比べると、骨粗しょう症の治療は確実に進歩しているので、きちんと治療をすれば椎体骨折のリスクを減らすことができます。
Q. では、椎体骨折の治療法についても教えてください。
A. 基本的には安静にしてコルセットを装着し、痛みに応じて鎮痛薬を用います。そして、根底にある骨粗しょう症の治療を行うといった保存的治療になります。しかし、安静にしていても効果が出ずに痛みが続き、骨の変形が進んでしまう場合は外科的治療が必要になります。
特に、痛みがある場合は身体を動かせない状態が続くことから廃用症候群といって、足の筋力や心肺機能が低下し、寝たきりの状態になってしまうことがあります。そのため、保存的治療で経過を見ながら、早期に外科的な介入をすることで廃用症候群に陥らないようにすることが大切だと思います。
Q. 保存的治療で様子を見るのはどのぐらいの期間ですか?
A. 以前は、保存的治療を3カ月程度続けてから手術を検討するのが一般的でしたが、最近では廃用症候群に陥らないために、保存的治療の期間が1~2カ月程度に短縮されてきています。早期の段階で外科的治療に踏み切る施設が増えてきている傾向があります。
Q. 外科的治療というのはどのような内容ですか?
A. さまざまな治療法がありますが、軽微な骨折の場合は、BKP(Balloon Kyphoplasty:経皮的椎体形成術)といって潰れた椎体内に骨セメントを入れて固める手術があります。全身麻酔は必要ですが、3mm程度の創2本で手術ができるので身体への負担が小さく、手術は20分くらいで終了します。患者さんの状態によっては、2~3日程度で退院も可能です。日本で10年以上行われてきた確立された手術で、低侵襲(ていしんしゅう:身体への負担が小さい)なのでご高齢の方でも受けていただきやすいかと思います。
![]()
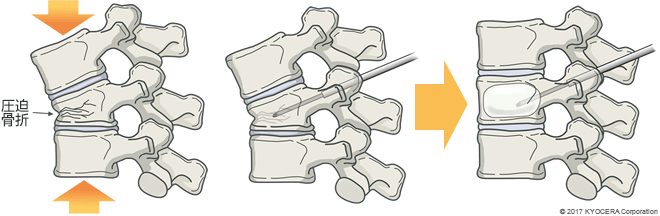
Q. 重度の椎体骨折の場合は、どのような手術になりますか?
A. BKPで対応できないほど骨折が進行している場合は、背骨にスクリューを打ち込んで固定する固定術となります。BKPよりも身体への負担が大きく、手術時間は最短で2時間弱程度、入院期間は1週間程度です。以前は皮膚を大きく切開して筋肉を切って行っていたため出血量も非常に多かったのですが、最近では経皮的な椎弓根(ついきゅうこん)スクリューによって、小さな創で筋肉を傷めることなく固定することも可能になってきています。
とはいえ私の考えとしては、できれば身体にかかる負担がより小さいBKPで対応できる段階で治療していただきたいです。もし腰痛や背中の痛みが続いているなら、早めに医療機関を受診されることをお勧めします。
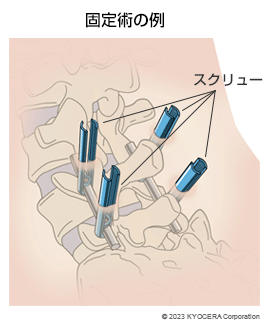
Q. 術後のリハビリについても教えてください。
A. 主に脚の筋力トレーニングとなり、理学療法士が付き添って進めていきます。歩行器、杖、平行棒などにつかまって歩行訓練をすることから始め、最終的には問題なく日常生活ができるような活動性を身につけることを目標としています。やはり、手術前に身体を動かさなかった期間が長ければ長いほど、リハビリ期間は長くかかりますので、そのためにも早期に外科的治療をすることが大切になります。
Q. 術後に気をつけるべきことはありますか?
A. BKPでも固定術でも、術後は創部の安定のためにコルセットを1~3カ月程度着けていただきます。その間は腰をひねったり、重たいものを持ったりといった動作は避けていただきます。また、手術をすればおしまいではなく、別の椎体骨折を起こさないために骨粗しょう症の治療を継続することが重要です。
 Q. 先生が治療において心がけていることを教えてください。
Q. 先生が治療において心がけていることを教えてください。
A. 患者さんを寝たきりにさせないことを一番の目標に掲げています。外科的治療に不安のある方は、手術を先延ばしにしたいお気持ちもおありかと思いますが、身体にかかる負担が小さい手術が適応となる時期を見逃さないようにお伝えしています。
また、骨粗しょう症は特に症状がないため治療効果がみえにくく、治療のモチベーションを維持するのが難しい面があります。しかし、椎体骨折を防ぐために治療を継続することがいかに大切かをお伝えしています。
Q. ありがとうございました。では最後に、先生が医師を志された理由を教えてください。
A. 子どもの頃、病気がちの父が入退院を繰り返す中、医療機関に行く機会が多く、医師の活躍を見たことがきっかけかと思います。実際に医師はやりがいのある仕事で、例えば椎体骨折の場合だと、手術した翌日から痛みがやわらいだと患者さんに喜んでいただけることもあり嬉しく思います。
Q. 最後に患者さんへのメッセージをお願いいたします。
リモート取材日:2025.1.23
*本文、および動画で述べられている内容は医師個人の見解であり、特定の製品等の推奨、効能効果や安全性等の保証をするものではありません。また、内容が必ずしも全ての方にあてはまるわけではありませんので詳しくは主治医にご相談ください。


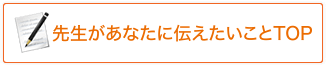
先生からのメッセージ
椎体骨折は、早期に診断を受けると、身体への負担が小さい方法で治療ができる可能性が高まります。