先生があなたに伝えたいこと
【深尾 繁治】脊椎脊髄疾患の手術は進歩し、以前よりもはるかに安全で低侵襲になりました。辛い痛みが長く続く場合は、手術をお勧めしています。

社会医療法人 岡本病院(財団) 京都岡本記念病院
ふかお しげはる
深尾 繁治 先生
専門:脊椎脊髄
深尾先生の一面
1.最近気になることは何ですか?
新型コロナの流行によって、これからの世の中がどう変化していくのかが気になります。医療を含めて、あらゆる面でデジタル化が加速しそうなので、乗り遅れないようにしたいです。
2.休日には何をして過ごしますか?
20年以上前から自転車競技をしており、現在も年間4~5回はレースに出場しています。そのため毎週末、自然の中で100kmぐらい自転車でトレーニングをしています。
このインタビュー記事は、リモート取材で編集しています。
 Q. 先生がご専門とされている「脊椎脊髄疾患の低侵襲手術」について教えてください。
Q. 先生がご専門とされている「脊椎脊髄疾患の低侵襲手術」について教えてください。
A. 低侵襲というのは、身体への負担が少ないことを意味します。具体的にいうと、手術で筋肉を切ったり剥離したり、骨を削ったりする量が少なく、出血が少ないということです。
Q. 低侵襲手術の対象となる脊椎脊髄疾患には、どのようなものがありますか?
A. 腰であれば、腰部脊柱管狭窄症(ようぶせきちゅうかんきょうさくしょう)をはじめ、腰椎椎間板ヘルニア(ようついついかんばんへるにあ)、腰椎変性すべり症(ようついへんせいすべりしょう)。首であれば、頚椎椎間板ヘルニア(けいついついかんばんへるにあ)や、変形性の頚椎症(けいついしょう)などが挙げられます。私は脳神経外科医なので、整形外科医に比べて首の疾患を取り扱うことが、若干多いかもしれません。
Q. 腰だけでなく、首のヘルニアもあるのですね?
A. 一般的によく知られているのは腰椎椎間板ヘルニアですが、首(頚椎)にも生じます。頚椎には7つの骨があり、その間に椎間板という組織があります。椎間板は、髄核(ずいかく)というおかゆのような柔らかい組織が、線維輪(せんいりん)という袋のような組織に包まれています。この袋が破れて中身が飛び出すと、それが神経根(しんけいこん)を強く圧迫し、手足に痛みやしびれなどの症状があらわれます。
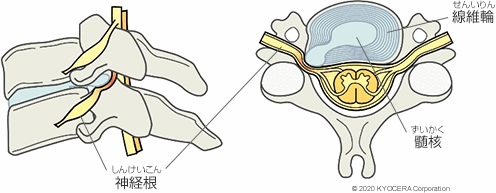
Q. 頚椎症のほうは、どのような疾患なのですか?
A. 頚椎症は加齢によって徐々に首の骨が変形し、神経が圧迫される疾患です。椎間板ヘルニアと同じく変形した椎間板、または肥厚した靭帯(じんたい)が神経根を圧迫すると手に痛みが生じ、脊髄まで圧迫すると手から足にまで症状が広がります。進行すると腕が使いにくい、お箸が持ちにくい、あるいは歩行中によくつまずく、歩きにくいといった症状も出ます。圧迫されるのが神経根か脊髄かによって、頚椎症性神経根症(けいついしょうせいしんけいこんしょう)か、頚椎症性脊髄症(けいついしょうせいせきずいしょう)に分かれます。これらは加齢が要因となるため、60~70代ぐらいの方に起こりやすい疾患です。一方、椎間板ヘルニアは40~50代の方が中心になります。
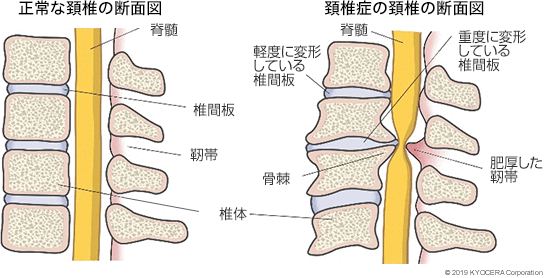
Q. これらの疾患は生活習慣が影響していますか?
A. 姿勢が大きく影響します。最近は「スマホネック」などと呼ばれる、首が前に倒れた後弯(こうわん)姿勢の方、あるいは首に自然な湾曲のないストレートネックの方などは徐々に変形が強くなりがちで、椎間板ヘルニアを起こしやすいです。また、長時間パソコンを使う姿勢も首に負担がかかり、症状が発現する要因となるため、注意が必要です。
Q. 頚椎椎間板ヘルニアや頚椎症は、どのような治療になりますか?
A. 基本的には保存療法となり、頚部カラー固定のほか、血流を良くして痛みを和らげるための電気治療やマッサージ、筋肉の動きを良くするストレッチなどの軽い運動などです。強い運動や頚部のけん引などは、症状が悪化することもあるため、私は勧めていません。こうした療法が取り入れられている施設もありますが、専門医のもとで慎重に進めることが重要です。
また、痛みが強い場合は、鎮痛薬や血流改善剤を用います。最近は薬の種類も豊富で、医療用麻薬の弱オピオイドなども強い痛みを緩和する効果が期待できます。ただし、先にご説明した神経根症であれば保存療法で緩和できるケースが多いのですが、脊髄症まで進んでいる場合は症状が治まりにくく、手術をお勧めしています。同じ疾患であっても、積極的な治療が必要か否かという見極めが求められます。
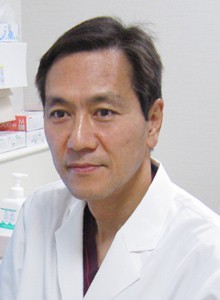 Q. どのような状態になると、手術を勧められていますか?
Q. どのような状態になると、手術を勧められていますか?
A. 痛みが強い、症状が悪化してきている、生活や仕事に支障が出ている、足に力が入らないなどの運動障害があるといったケースは、手術を勧めています。痛みだけで手術することに躊躇される方もおられますが、痛みが長期にわたると非常に辛いものです。現在は、昔に比べて手術の安全性が高まり、安心して受けていただけるので、治療の選択肢の一つになっています。
Q. どのような手術なのですか?
A. 大きく分けて、除圧術と固定術の2種類があります。神経を圧迫している組織を取り除く手術と、関節がゆるんで不安定な部位を金属のケージなどで固定する手術です。以前は皮膚を大きく切開し、骨に付着している筋肉を大きく剥離して手術を行っていました。しかし今は、知識と技術と器具が進歩し、半分程度の大きさの切開で手術ができるようになっています。
Q. それが冒頭で教えていただいた低侵襲手術ですね?
A. はい。創を小さくできれば、身体へのダメージが軽減されます。特に私たち脳神経外科医は、わずかな切開で顕微鏡を使って術野(手術の際に目で見える部分)を拡大しながら手術を行っています。それにより、両手を自由に使って精度の高い手術ができるうえ、何かが起きたときにもすぐにリカバリーが可能です。手術時間も短縮され、患者さんと医師、双方にとって負担が少なくなり、手術に対するハードルの高さも以前とはかなり違ってきています。
最も低侵襲な手術は、鍵穴式手術といって骨に8ミリ程度の穴を開けてそこから組織を取り除くものです。ただし、適応となるのは若い方にみられる神経根症だけです。多くの場合は、再発を防ぐため組織を十分に除去して固定する手術が一般的です。
![]()
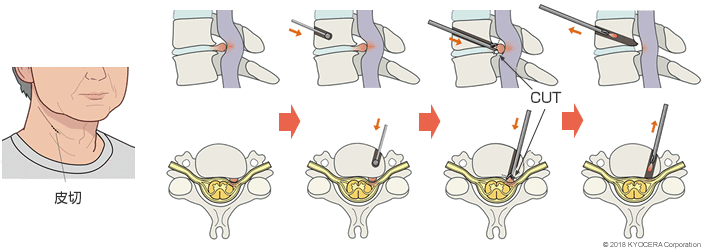
Q. 術後の流れを教えてください。
A. 入院期間は10日~2週間程度で、基本的に手術の翌日からリハビリを行います。ご高齢の患者さんが多く、数日でも寝たきりになっていると動きにくくなるため、早期に歩行訓練をスタートします。作業療法といって、手を使うリハビリなども含め、理学療法士や作業療法士のもとで全身に働きかけるリハビリを行います。
退院後は正しい姿勢を心がけ、重いものを持つことや長時間の中腰姿勢をできるだけ控えていただきます。また、首・腰の椎間板ヘルニアは早期に再発する可能性もあるため、1カ月程度は安静が必要です。首は頚椎カラーを、腰はコルセットを除圧術であれば1カ月、固定術であれば3カ月程度は装着していただきます。
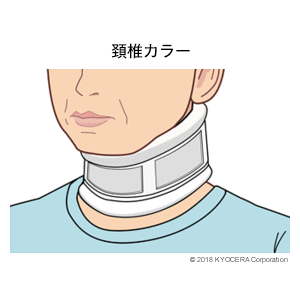
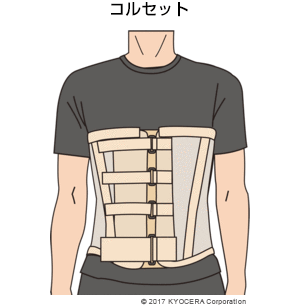
 Q. 脊椎脊髄の疾患を予防する方法はありますか?
Q. 脊椎脊髄の疾患を予防する方法はありますか?
A. 大切なのは、しっかりとした骨と筋肉をつくることです。そのためには、栄養バランスのとれた食事と運動習慣、適度に日光に当たるなどの心がけが大切です。骨粗しょう症が加わると骨の変形も強くなるので、しっかりと予防するとともに、日常生活の中で正しい姿勢を心がけましょう。
Q. 手術のやり方は、今後ますます進歩していくのでしょうか?
A. 手術機器が大きく進歩しているので、今後ますます変わっていくでしょう。当院でも今春、術中にCT撮影をして3次元でモニターを見ながら手術ができるナビゲーションシステムを取り入れました。1ミリの誤差もなく部位を特定できるため、まさに神の手のようです。より安全性が高まり、合併症もなくなりました。まだ全国的には多くありませんが、顕微鏡を併用したナビゲーション治療も可能で、筋肉もほとんど剥離せずにすみ、ますます侵襲が少なくなっています。この先は、こうしたシステムがなければ手術ができないような時代がやってくるかもしれません。
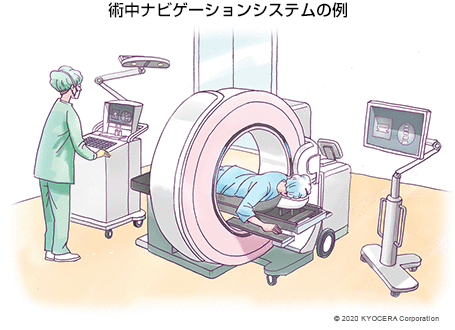
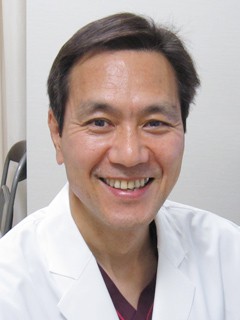 Q. それは患者さんにとって、ますます安心ですね。では最後に、先生の座右の銘を教えてください。
Q. それは患者さんにとって、ますます安心ですね。では最後に、先生の座右の銘を教えてください。
A. 当院の理念である「慈仁」、慈しみの心ですべての命と平等に向き合うこと、です。それに加え、当院の憲章にある「患者さんに対して、わが子、わが親、わが兄妹という気持ちで接する」ということをモットーにしています。家族である患者さんに対してリスクの高い治療はできないので、できるだけ侵襲が少なく、回復の早い、最良の治療を提供することにつながります。
そうすることで、患者さんには「先生に診てもらえてよかった」「手術してよかった」と喜んでいただけることも多く、医療従事者としてやりがいを感じています。
Q. 最後に患者さんへのメッセージをお願いいたします。
リモート取材日:2020.10.29
*本文、および動画で述べられている内容は医師個人の見解であり、特定の製品等の推奨、効能効果や安全性等の保証をするものではありません。また、内容が必ずしも全ての方にあてはまるわけではありませんので詳しくは主治医にご相談ください。


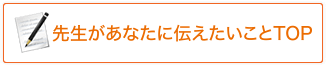
先生からのメッセージ
脊椎脊髄疾患の手術は進歩し、以前よりもはるかに安全で低侵襲になりました。辛い痛みが長く続く場合は、手術をお勧めしています。