先生があなたに伝えたいこと
【山川 知之】腰部脊柱管狭窄症や腰椎椎間板ヘルニアなどは、内視鏡を用いた低侵襲手術によって、早期に社会復帰ができます。

えびえ記念病院
やまかわ ともゆき
山川 知之 先生
専門:脊椎
※股関節の疾患について、詳しくお話しをされているページがございます。こちらをご覧ください。
山川先生の一面
1.最近気になることは何ですか?
寺社仏閣に興味があります。子どもを連れてお寺巡りをして御朱印を集めたり、近所に大きな神社がいくつかあるので、そこをランニングしたりもしています。
2.休日には何をして過ごしますか?
月に1回ゴルフをするほか、10年ほどマラソンを続けています。100kmマラソンを3回完走したことがあり、今も自宅から病院まで約14kmをランニングで通勤することもあります。走っていると"無"になれるので好きです。
このインタビュー記事は、リモート取材で編集しています。
Q. 腰椎の疾患で悩まれている方は多いと思います。代表的な疾患を教えてください。
A. 高齢社会の今、圧倒的に多いのが骨粗しょう症による椎体圧迫骨折(ついたいあっぱくこっせつ)です。骨が押しつぶされるように変形する疾患で、"いつのまにか骨折"と呼ばれています。身長が縮んで前傾姿勢になっている方に多くみられます。
当院に来られる患者さんに多いのは、腰部脊柱管狭窄症(ようぶせきちゅうかんきょうさくしょう)や腰部椎間板(ようぶついかんばん)ヘルニアです。
Q. 腰部脊柱管狭窄症とは、どのような疾患なのですか?
A. 名前の通り、背骨や椎間板(ついかんばん)、黄色靱帯(おうしょくじんたい)などで囲まれた脊髄の神経の通り道である脊柱管が狭くなる病気です。加齢とともに骨が縮み、椎間板が突出して神経に当たる、あるいは黄色靭帯が厚くなってたるみ、神経に当たることで脳が痛みとして認識します。腰部の神経は足にも通じているので、腰だけでなく足にも痛みが出てきます。
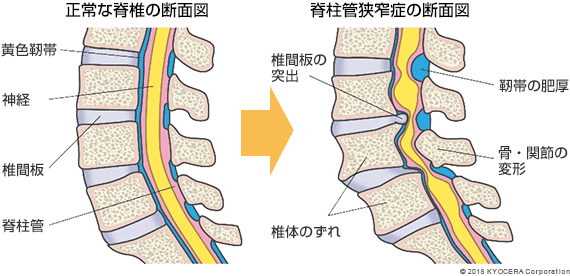
Q. 症状に特徴はありますか?
A. 間欠性跛行(かんけつせいはこう)が最初の症状になります。歩行中に足の痛みやしびれを感じ、少し休憩するとまた歩けるというもので、歩ける距離が徐々に短くなっていきます。進行すると、寝ているときにも痛みを感じるようになります。高齢の方に多くみられる疾患です。
Q. 腰椎椎間板ヘルニアについても教えてください。
A. 椎間板は、繊維輪(せんいりん)という硬い殻で覆われたゼリー状の髄核(ずいかく)から成り、椎骨と椎骨の間のクッションの役割を果たしています。これが何らかの衝撃やぎっくり腰などによって、繊維輪の後ろ側が破れて中の髄核が突出し、神経を刺激します。何かが突出すること自体をヘルニアといいます。中央ではなく、左右いずれかに飛び出ることが多いため、左足あるいは右足の片方だけに痛みが生じます。
腰部脊柱管狭窄症が軽い症状から徐々に進行していくのに比べ、腰椎椎間板ヘルニアは直接神経に当たるので、最初から臀部から足にかける痛みの程度がかなり強いのが特徴です。
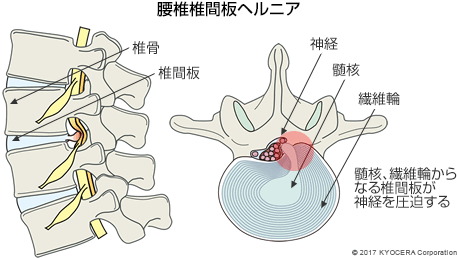
Q. 腰椎椎間板ヘルニアになる原因は何でしょうか?
A. 比較的若い方に起こりやすく、20代と40代の2極性があるといわれ、さまざまな原因が考えられます。一つは家族性で、遺伝的に繊維輪が破れやすい。もう一つは喫煙。さらに、重量物を持つ、あるいは同じ姿勢を続ける人に多いといわれています。20代に発症者が多いのは、それまでは部活動などで運動習慣があったが、学校を卒業して運動する機会が減り、仕事などで同じ姿勢を長時間とり続ける状況が影響している可能性があります。
Q. これらを予防する方法はありますか?
A. 加齢とともに進行する腰部脊柱管狭窄症は予防しにくいのですが、腰椎椎間板ヘルニアの場合は筋力維持が大切になります。腹筋が低下すると、もともと備わっていた腰部のコルセット機能を失うことになり、椎間板に負担がかかってしまいます。筋力維持のための運動に加え、重量物を持たないこと、同じ姿勢を続けないことが予防につながります。
 Q. よくわかりました。では、治療法について教えてください。
Q. よくわかりました。では、治療法について教えてください。
A. 痛みが腰だけの場合は、鎮痛剤の服用となります。さらに足にも神経的な痛みがあれば、神経に対する痛み止めも追加します。中等度の痛みであれば、ブロック注射を行うこともあります。神経に近い箇所に打つ硬膜外ブロック、飛び出ている神経自体に注射する神経根ブロックなどを組み合わせながら、外来通院での治療となります。これは、腰部脊柱管狭窄症、腰椎椎間板ヘルニアともに共通です。
Q. 運動療法も効果がありますか?
A. 当院では、リハビリ室で運動指導を行っています。筋力維持のための体操とストレッチを何度か行い、痛みが和らぐようであれば、骨盤を固定して腰部を引っ張る牽引療法を行います。歪んでいた椎間板が平行になって症状が緩和される、あるいは縮んでいた脊柱管がストレッチによって広がり、ヘルニアが緩和されるケースもあります。
Q. どういった場合に手術になりますか?
A. 最初から足の動きが悪い、またはマヒ症状がある、排尿・排便に支障がある、痛みが強いという場合は、MRI 検査を行ったうえで手術を検討します。足の麻痺や膀胱直腸障害が長引くと治癒が困難になるため、その場合はこちらから手術を提案します。ただし、手術によって症状が治まる確証が得られるかがポイントになるため、MRI画像での診断とブロック注射の効果を照らし合わせて見きわめます。
Q. どのような手術か教えてください。
A. 腰椎椎間板ヘルニアにおいては、腰椎椎間板ヘルニア摘出術になります。一般的には、皮膚を3~5cm程度切開し、骨から筋肉を剥がして摘出するのですが、そうすると腰部の筋力が低下し、手術後に違和感が残ることがあります。入院も12週間程度必要になります。
そのため、当院ではできるだけ患者さんに侵襲(しんしゅう:身体に対する負担)を与えず、早期に社会復帰していただけるよう、内視鏡を使った経皮的内視鏡下腰椎椎間板ヘルニア摘出術(PED法(ペド法))を行っています。うつ伏せになって全身麻酔を施し、直径7mmの筒を挿入して内視鏡で椎間板を観察しながらヘルニアを摘出します。術後は約3時間で歩行ができ、翌日には退院できます。虫に刺された程度の創(きず)しか残らず、患者さんの身体への負担が少ないことがメリットです。
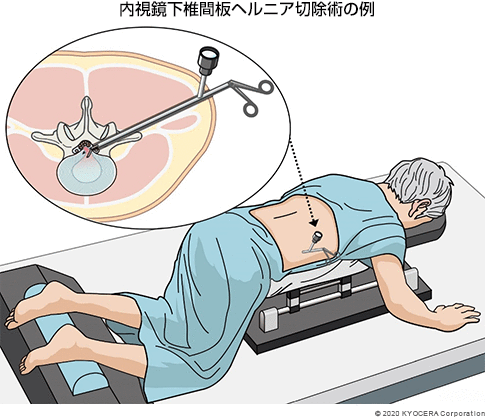
Q. 腰部脊柱管狭窄症の手術も内視鏡でできるのでしょうか?
A. はい。脊柱管を拡大するために脊椎の後ろ側にある椎弓(ついきゅう)を切除するのですが、当院では内視鏡を用いています。内視鏡下椎弓切除術(MEL)といって、約15mmの創で内視鏡を挿入し、神経に当たっている骨や黄色靭帯などを切除します。患者さんには、親指の爪ぐらいの大きさの創ができると説明しています。
こちらも筋肉を傷つけずに穴を開けるようなイメージで内視鏡を挿入し、外側を傷つけることなく内部を治療する手術になります。この疾患は、2カ所に処置を要するケースが多いのですが、内視鏡を用いれば1カ所の創で2カ所とも処置することが可能です。術後は血が溜まらないように排出する管を術後1日挿入し、出血が治まってから管を抜去して、体調に問題がなければ退院となります。従来は3週間ほど入院が必要でしたが、現在は5日間程度となっています。
![]()
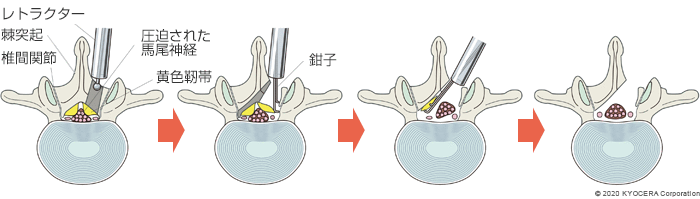
Q. 術後はどのようなことに気をつければよいですか?
A. しばらくは手術したことを忘れないことです。というのも、術後あまりにも身体に違和感が残らないため、患者さんが手術したことをうっかり忘れて、重いものを持ったり、腰をひねる動作をしたりすることがあります。最低でも、術後1カ月ぐらいは無理されないようにお願いしています。ただし、その先は制約のない生活を存分に楽しんでいただきたいです。
 Q. 先生が整形外科において、独自に取り組まれていることはありますか?
Q. 先生が整形外科において、独自に取り組まれていることはありますか?
A. 私は、腰椎椎間板ヘルニア摘出術にPED法を用い始めて5年になり、これまでに300~400件の症例を手掛けてきました。現在は、これを腰椎すべり症の治療や頸椎の手術にも使用しています。PED法を活用することで、患者さんの身体的な負担が大幅に軽減でき、手術時間も短縮できます。私は脊椎以外にも、手や各関節なども専門としていますが、今後ますます多方面で内視鏡を活用した手術の可能性は広がっていくと考えています。
Q. ありがとうございました。では最後に、先生が医師を志された理由をお聞かせください。
A. 実家が接骨院で、骨の模型が身近にある環境で育ちました。小学5年から大学までサッカーをしていたのでケガをすることもあり、たびたび整形外科にお世話になったことも影響しているかもしれません。
今の自分のスタイルができたのは、現場で最初に指導していただいた恩師が、幅広い専門分野をお持ちだったので、その影響だと思います。これからもあらゆる手術手技において、妥協なく最善を目指したいと思っています。
Q. 最後に患者さんへのメッセージをお願いいたします。
リモート取材日:2020.8.28
*本文、および動画で述べられている内容は医師個人の見解であり、特定の製品等の推奨、効能効果や安全性等の保証をするものではありません。また、内容が必ずしも全ての方にあてはまるわけではありませんので詳しくは主治医にご相談ください。


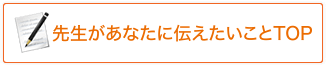
先生からのメッセージ
腰部脊柱管狭窄症や腰椎椎間板ヘルニアなどは、内視鏡を用いた低侵襲手術によって、早期に社会復帰ができます。