先生があなたに伝えたいこと
【山本 精三】何より、行動の自由がずっと続くというのは大事なことです。

国家公務員共済組合連合会 虎の門病院
やまもと せいぞう
山本 精三 先生
専門:人工膝関節・人工股関節
※こちらのページでは人工膝関節についてお話しされています。人工股関節についてはこちらをご覧ください。
山本先生の一面
1.好きな言葉
"Start Today, Tomorrow Never Comes"
今日から始めよう。でなければ明日は永遠にやってこない。
2.最近気になることは何ですか?
経済学者のガルブレイスという方の著書を読みました。終戦の年に日本に来て調査をして、戦後復興や原爆投下などについて様々な考えを提示した方です。今の日本に見られる、地方自治体のトップの人が元気な現状も予測したりしていて、大変興味深いものがありました。
Q.先生ご自身もひざの痛みを感じておられた時があったとうかがいました。どのような痛みだったんでしょうか?
 アメリカに留学していた時、完全なクルマ社会、日本とは違う食生活、そのうえ体を動かす習慣もなかったので、大変太ってしまいました。日本に帰ってきたら通勤、階段の昇り降りでひざの痛みを自覚するようになりました。
アメリカに留学していた時、完全なクルマ社会、日本とは違う食生活、そのうえ体を動かす習慣もなかったので、大変太ってしまいました。日本に帰ってきたら通勤、階段の昇り降りでひざの痛みを自覚するようになりました。
痛みはいつも左側です。成長期に外傷があったということでそれが大元の原因だろうと思います。ひざの痛みで興味深いのは、例えば診察所見あるいはMRIで半月板損傷がみられたとしても、それがすぐに痛みにつながるわけではないということです。痛みは何かのきっかけで出てきます。私の場合は、体重の増加がきっかけになったんだろうと思います。
Q.先生は10kgの減量で痛みを解消されたということですが、すごいですね。
それほど減量は有効なのでしょうか?
私は元々がそんなに太っているわけではありませんので、10kgの減量がすごいことかどうかはわかりませんが...。例えば3kgでも減らしていただくと通常のひざの痛みであれば楽になります。なぜなら、歩いているときも階段をおりるときも、体重の2~3倍、あるいはもうすこしスタスタとすばやく降りると5倍くらいの負荷がかかりますので、仮に3kg落とすと、すぐに10数kg分の負荷がなくなるということになります。すると体感的にもかなり痛みがなくなるということがありますね。
Q.それでまず、体重を減らすことを患者さんに奨められているんですね。
私のところに来られる患者さんは、既にかなりの痛みが出ておられる方が多いのです。体重を減らすために内科の先生方は「運動しなさい」とおっしゃいますが、では運動は何をするんですか、と患者さんに聞くと「散歩」という答えが返ってくることが多くあります。しかし実際は、痛みを伴いながら歩くのは、ひざや軟骨によくないことがあります。ですから、私の患者さんは運動を増やすわけにはいかないということになりますので、食生活から変えていかないと・・・。そのため、体重そして食事のことをかなりうるさくいっています。
Q.具体的にはどのように指導されておられるんでしょうか。
 ひざの病気で入院した患者さんの中で肥満のある患者さんには、原則的に、カロリー制限、糖尿病食のようなものを出しています。ただ通院されている患者さんについては、毎回体重を測定することと、カロリー制限の指導をしています。例えば、今は身長150cmくらいのご高齢の方が多いと思いますので、1400kcal。あるいは、活動的な人だと1600kcalくらいを目指してもらい、それでも減らない人は200kcalずつくらい減らしていくという風にしています。よく話を聞くのは、和菓子が好きな人が多いということですね。「間食はだめですよ」と、カロリーだけでなく食生活全体も指導しています。
ひざの病気で入院した患者さんの中で肥満のある患者さんには、原則的に、カロリー制限、糖尿病食のようなものを出しています。ただ通院されている患者さんについては、毎回体重を測定することと、カロリー制限の指導をしています。例えば、今は身長150cmくらいのご高齢の方が多いと思いますので、1400kcal。あるいは、活動的な人だと1600kcalくらいを目指してもらい、それでも減らない人は200kcalずつくらい減らしていくという風にしています。よく話を聞くのは、和菓子が好きな人が多いということですね。「間食はだめですよ」と、カロリーだけでなく食生活全体も指導しています。
ちなみに、個人的には野菜を中心にした食生活を意識しています。今は体重が減ってしまったので厳密にはしていませんが...。
Q.女性の患者さんにとって、体重を減らしなさいという指導はつらいものがあると思うのですが、「えっ」という反応が多いのではないですか。
多いですね。ご高齢の方、特に女性で難しいのは、やせると「がんになったんじゃないか」といわれたり、急にやせると顔にしわができて、かえって老けた印象をもたれてしまうということがあるそうで、そのあたりはよく事前に説明しておかないといけないんですよ(笑)。
しかし体重を減らしていただくとひざの痛みが楽になり、体の動きも大変よくなります。
顔だけのイメージを考えるのではなく、体全体のイメージを考えていただきたいですね。太ってよちよち歩いているイメージと、顔は年並みのしわが出るかもしれないですが、少しやせて、颯爽と歩いているイメージとどちらが若々しく見えるかというと、それはやはり颯爽とスタスタ歩いている人の方が若々しく見えるのではないでしょうか。そのイメージを持ってくださいとお願いしています。何より、行動の自由がずっと続くというのは大事なことです。
Q.少し話が変わりますが、先生は、変形性ひざ関節症の患者さんが板橋区にどれほどおられるか、という研究をされたとうかがいました。その結果から患者さんに参考になる情報がありますか。
 板橋区の研究は、東京都老人医療センター(現 東京都健康長寿医療センター病院)と東京大学とが一緒に行ったもので、非常に貴重な疫学研究となっています。板橋区で平均年齢77歳前後の約1000名の方にご協力いただき、コホートスタディー*を行いました。
板橋区の研究は、東京都老人医療センター(現 東京都健康長寿医療センター病院)と東京大学とが一緒に行ったもので、非常に貴重な疫学研究となっています。板橋区で平均年齢77歳前後の約1000名の方にご協力いただき、コホートスタディー*を行いました。
検診とレントゲン撮影をお願いした結果、わかったことをいくつか紹介します。
*コホートスタディー:一定の地域集団のなかで、いろいろな要因を検討し、それぞれがもつ因子を把握して、その因子を持っている人と持っていない人では、どのような病気になるか、またはどのような病態になったかを分析できる研究のこと。
(1)男性の約4割、女性の約6割が軽い変形性ひざ関節症であり、女性の方に、より変形の度合いが強い。
(2)この男性4割、女性の6割の方は、レントゲンを見ると軟骨がすり減っているものの、痛みなどの症状が全ての方に出ているというわけではない。
...ということでした。
(2)については、軟骨がすり減ったからといって、すぐに痛みが出るというわけではないことがわかりました。軟骨そのものには神経がないためです。ある程度症状が進まないと痛みが出てこないというのは悪いことではありますが、いいことでもあります。つまり、すり減ってはいても、軟骨が残っていれば、体重を減らすなどの工夫で、痛みが出てくる前に予防が可能なのではないか、と考えるからです。
また、この研究の中で非常に重要だったのは...
(3)ひざに痛みがある人とない人とを分けてそのグループを比較すると、
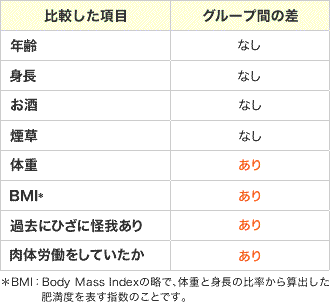 左の表のような結果が出ていることです。
左の表のような結果が出ていることです。
痛みがあるグループとないグループを比較すると、「年齢」や「身長」「お酒」「煙草」をたしなむかどうかによっての差はみられませんでしたが、「体重」「BMI」「過去にひざに怪我あり」「肉体労働をしていたかどうか」では、差がみられました。特に、「体重」と「BMI」では、女性によりはっきりと差がでていました。
現在、痛みがある患者さんに対して「過去に怪我をしたのでひざに痛みが出てきているのかもしれません」「過去に肉体労働をしていたから、ひざに痛みが出てきているのかもしれません」といっても、納得はしていただけても前向きな発言ではありません。その他にも、痛みのある人は男性より女性の方が多いですし、脚の形もO脚の方が多いということがわかっているのですが、それも患者さんが変えられるものではありません。ですから、「体重を減らしていきましょう」ということになるのです。
Q.患者さんに対して体重を減らすことの大切さを訴えておられる先生ですが、最近は加えてロコモティブシンドロームについても積極的にお話されているそうですね。ロコモティブシンドロームについて教えてください。
 ロコモティブシンドローム(ロコモ)を意識するということは、ひとことでいうと「寝たきりを防ぐ」ということです。確かに、ひざが痛くてすぐに「寝たきり」というところまではいきません。しかし「要介護」となる場合が多いのではないかと思います。
ロコモティブシンドローム(ロコモ)を意識するということは、ひとことでいうと「寝たきりを防ぐ」ということです。確かに、ひざが痛くてすぐに「寝たきり」というところまではいきません。しかし「要介護」となる場合が多いのではないかと思います。
内科では、高血圧、糖尿病、高脂血症を'死の三重奏'といっていますが、肥満を入れると'死の四重奏'になります。整形外科医の立場からいいますと、死には至らないけれど寝たきりになる'寝たきり三重奏'が、関節痛、骨折、腰痛です。少し衝撃的で悲観的な言葉なので、和らげるために「ロコモティブシンドローム」と表現していると思います。そういう意味で、患者さんに浸透しやすい言葉ですね。
そして、肥満を加えると'寝たきり四重奏'ともいえます。肥満だけでは寝たきりにはなりませんが、肥満はそれぞれの項目に付随して、必ず寝たきりを引き起こしていくことになるでしょう。
ロコモの3大原因として、ひざを含めた関節炎、脊柱管狭窄症(せきちゅうかんきょうさくしょう)などによる腰痛、骨粗鬆症(こつそしょうしょう)による骨折があげられますが、骨粗鬆症による骨折については、かなり有効な薬剤がでてきており、現在、カナダとか北欧では骨折の頻度が減ってきているという報告があります。近い将来日本でも、骨折の頻度は減ってくるのではないかと思います。ですが、残念ながら軟骨を増やす薬は今のところありませんので、関節炎についてはまだまだ減らないでしょうし、増加している状況だと思います。
Q.ロコモを意識した方がよいのは、またロコモーション・トレーニングをやったほうがいいのは何歳ぐらいからですか。
 それはいい質問ですね。私が自分の痛みに気づいたのは40歳代からです。まず、ひざに何らかの怪我があった人については、早くから意識することが必要だと思います。そして肥満に関していうと、例えば肥満の強いお相撲さんでは30歳くらいでも、レントゲンを撮ってみると、かなりの人に変形性ひざ関節症が起こっています。もちろんこの場合は肥満に加えて怪我も多いことがあるでしょう。
それはいい質問ですね。私が自分の痛みに気づいたのは40歳代からです。まず、ひざに何らかの怪我があった人については、早くから意識することが必要だと思います。そして肥満に関していうと、例えば肥満の強いお相撲さんでは30歳くらいでも、レントゲンを撮ってみると、かなりの人に変形性ひざ関節症が起こっています。もちろんこの場合は肥満に加えて怪我も多いことがあるでしょう。
そういう怪我をした人や肥満の人を外して一般的な人に話をするのであれば、更年期に当たる少し前くらいからが意識をするタイミングではないかな、と思っています。まずは女性ホルモンの低下が起こり始め、40歳代後半は劇的にホルモン・バランスが変化します。骨の代謝、軟骨の急な変性が起こりやすいのです。そういう時に、肥満や大きな怪我をするとなかなか治りにくい。ですので、関節の変化が起こりやすい40歳代半ばくらいから、注意していく必要があると思います。
Q.思ったより早いように感じました。
そうですね。実際、50歳代くらいから転倒による骨折が増加します。骨折の場合は、「転んで骨折しました」と、急に運ばれてきます。しかし先ほどお話しましたように、軟骨は少しすり減ってもわかりません。ご存知かもしれませんが、基礎代謝量は50歳~60歳頃になると急激に落ちてきます。そのあたりで注意していないと、体重増加が絶対に起こってきます。同じ体重であっても、筋肉が落ちてきて体脂肪が増えていきます。そういう変化もホルモン・バランスの変化を受けて起こってきますので、その変化が起こる前あたりで意識しておくことが大変重要ではないかと思います。
Q.ご高齢のご家族のために、関節痛や人工関節について情報を探したり、先生にお話をうかがって勉強されてこられた方が、このインタビューを読まれて、「私もそろそろロコモかな」と、ご自身の問題と認識いただけるとうれしいですね。
 人工関節の手術をする時、娘さんが付いてこられることがあります。そして親子の体型が「似ているな」と思えば必ず「気をつけなさいね」といっています。親子とも肥満傾向であったり、あるいは親がO脚で娘さんもO脚の場合というのはよくあることです。もちろん、痛みが出てくるのは体重や脚の形だけが要因ではありません。肥満があっても、ひざが悪くならない人もいらっしゃいます。遺伝的な要因があるということもわかってきています。
人工関節の手術をする時、娘さんが付いてこられることがあります。そして親子の体型が「似ているな」と思えば必ず「気をつけなさいね」といっています。親子とも肥満傾向であったり、あるいは親がO脚で娘さんもO脚の場合というのはよくあることです。もちろん、痛みが出てくるのは体重や脚の形だけが要因ではありません。肥満があっても、ひざが悪くならない人もいらっしゃいます。遺伝的な要因があるということもわかってきています。
ロコモーション・トレーニング(ロコトレ)は、40歳代や50歳代でやるようなトレーニングではないと思います。もう少し高齢になってからやる
トレーニングで、ひざの悪い人だけではなく、腰痛のある人、骨粗鬆症のある人など、ロコチェックにあてはまる人について奨められるものです。60歳を超えたくらいからは、こういうことをチェックしていくというのが大事ではないでしょうか。
関係ない話かもしれませんが、雨の日は散歩しない、冬も寒いから散歩しない、という方がおられます。室内で規則的な運動がどれだけできるかということを考えると、ロコトレを提示して、実行していただくことは非常に大事だと思います。とはいっても、自宅でひとりでトレーニングを継続して行うことは難しいことだと思っていますので、定期的に様子を聞いて、励まして続けてもらうことも私の仕事だと考えています。
つまりは、規則正しい生活をして、間食をせず、適度な運動習慣をつけておく...そういったことが大切です。
Q.最後に患者さんへのメッセージをお願いいたします。
取材日:2009.8.6
*本文、および動画で述べられている内容は医師個人の見解であり、特定の製品等の推奨、効能効果や安全性等の保証をするものではありません。また、内容が必ずしも全ての方にあてはまるわけではありませんので詳しくは主治医にご相談ください。


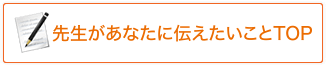
先生からのメッセージ
何より、行動の自由がずっと続くというのは大事なことです。